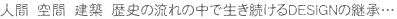建築家としての原点
二階の窓辺からは青々とした松並木とその向こうに小学校のグランドの広々とした土色が見え隠れしていた。 6帖一間の事務所で木製の引き違い窓からは、強風時は雨が滲み込んできた。27才の春、昭和61年の春であった。 私が設計事務所を開設した頃のいま想い出される風景である。 先々の様々な不安を感じながら、なぜか幸福だったのを覚えている。 一台の製図版と青焼きのコピー機一台、そして学生時代買った建築書。 これがせめてもの建築家としての心意気を持続させてくれた様な気がする。 とにかく何もないところからのスタートだった。しかしその時季節は春。 住宅(借家)の二階にあるそのアトリエは、悲しいほど明るかった。 築30年は経つであろう借家の波トタンの外壁は、私のその春の気持ちとは対極をなすべき錆色でむしろ心を奮い立たせた。 「建築」とは「人間」と読むのか。 私の建築に対する取り組み方は正しかったのか。 人間の心の深い淵に滲み込んでゆく「建築」という物理的なもの。
最近の世の中全体のスピードにはなかなかついて行けない。 私達人間は、もっとゆっくり歩むべきではないだろうかと思う。 携帯もパソコンもワープロさえもまだ一般には普及してなかった頃に事務所を始めたせいか私は少々の不便には慣れている。 人間の手による行為を信じ、そのプロセスの重層が必ずしも私たち人間を時代遅れにはしないことを再考すべき時なのではないだろうか。
建築はその建築家の心の襞の数だけ深みを感じさせてくれる。 色彩も形態も機能も全てそれを表現する。 悩み抜く事の肯定、瞬時には表現されない人間の手による行為としての建築表現。 いま私たち建築家はあの頃の春に帰るべきではないのか。 建築は風の香り、建築は何とも表現できない熱い心の形。 建築はいわば人間を包み込むシェルター。 気負わず心の中を表現できたらそれが建築。 そして、できれば美しく。 手書きの図面で今でも幸福。 右手のHBの黒い粉跡が建築家としてのせめてもの証し。 ネガティヴなものとポジティヴなものの錯綜の中、春の香りが私の不安な心に平穏な光を運んできてくれた。 時代が移りゆくとも、人間は変わらない。 人間の本質的キャパシティに何の増減もありはしないのだ。 もっとゆるやかに、もっと自己を深く見つめてこれからも歩んでいきたい。 建築というものはもっとシンプルなものではないか。 人間との結がりにおいて、生命との関連において、気負うべきものは何もない。 今まで通り私はゆるやかに建築を創り続けてゆくだけ。 できるだけ美しく。 そして優しく。
(伊嶋洋文地域環境建築設計室 代表)