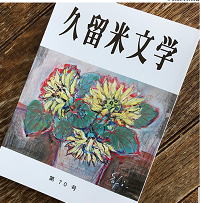思い出 (2023/2/17)   旧古賀町役場 (古賀市立歴史資料館から) 幼年時代の思い出から得た神聖で貴重なものなしには、 人は生きてゆくこともできない。(ドストエフスキー・作家の日記から) 敗戦直後の少年時代。 赤く染まったレンゲ畑、澄み切った小川に戯れるメダカ。 遠くに連綿とやさしく連なる山々。 どこまでも続く白砂、抜けるような青空。 暗くなるまで遊びにふけったお宮、走ると軋む小学校の廊下。 ほんの数10年足らずのあいだに、その山々は容赦なく削られ、 砂浜はテトラポットの冷たい海にと変貌してしまった。 戦後十年、なにもない時代だったが、自然があった。年を取ったせいか、なにごとも悲しいほどに懐かしく思えてならない。  古賀駅 古賀駅1章 地獄絵 両親は文男を仏教関係の幼稚園にいれた。4歳のときで ある。園長先生は、ナベ蓋のような丸い顔にソラ豆に似た 小さな目、丸縁メガネをかけたおっとりした人であった。 いっぽう、園長の奥さんはいつもイライラした痩せ型の 人で、50歳は過ぎていたかと思う。雀の巣に似た髪型が奥 さんの表情を、いっそう神経質なものにしていた。 しゃり出ては、子供らになにかと指示し、説教した。文男 はそれがイヤでならなかった。先生たちも奥さんの言動に は口を挟まなかった。 を降ろした暗い講堂に皆、頭を並べて横にされた。 は園長の奥さんで、文男は息を殺し寝たふりをした。 ひっつけますよ」そう言いながら、頭をならべ寝ている園 児の間を行ったり来たりした。声をたてる者はいない。 あけてみた。しかし、辺りが暗いため、奥さんの影すら見 えず、文男にとっては、牙をむいた獣が闇の中をうろつい ているようなものであった。安眠のときが恐怖の時間に変 えられてしまった。 り手を引っぱられ、物置きに閉じ込められてしまった。い つか自分も同じように、あの真っ暗な物置きに押し込まれ るんじゃないだろうか。泣き叫ぶ仲間の、切り裂くような 声を耳にしながら震えていた。 悪いことをしたり嘘をついたりすると、こうなります」 壁にかかった一枚の大きな障壁画のまえに座った。畳一 枚ほどの絵の縁は虫が食った小さな穴が無数にあった。 っている。悶え苦しみながら針山に登る人々、麓では閻魔 大王が足を踏んばり、先が内に曲ったハサミのようなもの で人の舌を引っ張り抜こうとしている。骨が浮き出るほど 痩せ細った人がムシロの上に横たわり、落ち窪んだ眼窩を 天に向けている。 じゃありません。かつては人間だった。でも、嘘をついた り悪いことをしたばかりに地獄に落ちた亡者なのです。 人は死んだらふつう、極楽浄土という平和で幸せな国へ 行きます。しかし、亡者は死んでも仏になれず、こうした 地獄でいつまでも苦しみ続けるのです」 地獄絵に描かれた人びとは、どう見ても悪人には思えな かった。馬上から亡者を追いかけ、鞭を振るう者の豪華な 着物に比べ、彼らの身なりのなんとみすぼらしいことか。 絵図に描かれた人たちは近所の豆腐屋のおじさんに似て いたし、幼稚園に来る途中に畑で汗を流している農家のお じいさんにも似ていた。このような人たちが地獄へ行くの なら、いずれ自分も地獄へ行くのではないか。その夜、静 まり返った布団の中で、まわりの世界が怖く、何度も目を 覚ました。妖怪のようなものが闇の中で蠢いているようで、 便所にも行けず、芋虫のように布団にくるまっていた。 人ではないだろう。「嘘をついたり、悪いことしたりして はいけません」子供らに説教していた奥さんは極楽浄土へ 行かれただろうか。地獄など現世だけで十分である。  2章 松ぼっくり 文男が7歳、長女の亜子が5歳、次女の君子が1歳、父 の帰宅は10時過ぎで、酒がはいっている日が多かった。し かし、遅くなる理由は他にあった。両親の口論から、それ がなにか、おおよそ見当はついた。 母は三人の子供に食事させたのち、幼い妹二人を風呂に 入れた。戸外にある井戸からバケツで水を汲み上げては、 炊事場の端に設けた風呂桶に水を張る。井戸と風呂を何度 も往復する母は、両手に下げたバケツの重さに、なんとか 耐えている風であった。風呂を沸かす材料は材木の切れ端 で、火の付きが悪い時には松ぼっくりも使った。 ある日の夕方、母や妹たちと家の近くに広がる松林に松 ぼっくりを拾いに行った。丸く大きくはじけたそれが一ヵ 所にたくさん落ちているのを見つけたときは、文男も亜子 も、まるで宝物を見つけたようにはしゃいだ。 持参した麻袋もほぼ一杯になったころ。鬱蒼と繁った松 林の奥から何者かがこちらへ近づいてきた。 「おくさん…」一瞬、母の顔が強ばった。背が低く、熊の ように背を丸めた男は不機嫌そうな顔で母を睨んだ。 「無断で他人の土地に入り、勝手に拾ってもらっては困り ますな」君子を抱いた母は泣き出しそうな顔で、 「す、すみません」何度も頭を下げた。 「泥棒と言われても仕方ないでしょ」母をしつこく責めた。 男は数キロに広がる松林の所有者で、すっかり恐縮して しまった母は、松ぼっくりが入った麻袋を地面に置き、 「今後、気をつけますから」幾度も頭を下げた。 君子が周りの雰囲気を感じ取ったのか、泣きだした。 「きょうのところは許してやるから、今後、気ぃつけな」 男は唾を吐き捨てると、林の奧に去っていった。文男た ちは手にした松ぼっくりを捨てると、母の後を追った。 「ケチなおじさんやね。松ぼっくり拾うと、木が枯れると やろか?」長女の亜子が尋ねた。が、母は答えない。 「ねっ、おかあちゃん。松の木が枯れると?」 「枯れたりはしないけど、黙って人さまのものを拾ったか あさんが悪かったんよ。……。そうそう」母はそういって、 「きょうはお父さんの給料日だし、お肉料理にしましょう」 「うん」いままで沈んでいた空気が春の光のように弾けた。 子供らを入浴させることは想像以上に大変であった。湯 加減を調整しながら、妹二人を入浴させ、そのあと次女に 寝巻きを着せながら、長女の体を拭いた。 ある蒸し暑い夜、母は、帰宅した父と口論の末、感情的 になった母が、味噌汁の入った椀を父に投げつけた。いま まで寝入っていた文男は突然の音に目を覚まし、襖の間か ら恐る恐る隣の様子を窺った。父が母を殴った。父が暴力 をふるったのは今回が初めてである。 「あなたが悪いんでしょ。悪いことをしておいて、人を殴 るなんて最低よ……」涙声で言った。父は黙ったまま、仁 王のようにつっ立ったまま。味噌汁を吸った背広は白く豆 腐穀で覆われていた。その夜の出来事は、文男の脳裏にフ ィルムのように焼き付いてしまった。 そのころからだった。父に幻滅した母は、長男の文男に 期待を向けた。母は付ききりで、勉強を教えようとした。 “古い”という字を一週間経っても書けずにいた。文男が 通っている古賀小学校の“古”という文字を指差し、 「あんたが通っている学校の名でしょ」ヒステリックに放 った。ときには机をたたいて叱った。文男はそばに控える 母から逃げだしたい一心で、勉強どころではなかった。 しかし、普段は優しい母で、子供らが眠る際、川の字に なって寝ている子供らに、毎夜、子守歌を歌った。 母は実の母親を知らない。戦時、大陸で母親を亡くした そうだが、それ以上は口にしなかった。 蛇足になるが、勉強について一切、干渉されなかった妹 二人は、彼女らが中学生のとき、担任の先生方から、 「どうしたら、このような子に育つのでしょうか?」おお よそ、そうしたことを、尋ねられたそうだ。 大学を卒業した二人は、ともに医学の道に進み、70を過 ぎたいま、コロナ対応に追われる毎日を送っている。  小学校運動場 小学校運動場3章 不安 片道10キロの通学は大変であった。というのも、学校の 裏に、真昼でも薄暗い森が広がり、迂回していたためであ る。山林を通り抜けることは学校で禁じられていた。 ある日、いつも連れだって下校していた小川進一と相川 健二と三人で、この山道を通り抜けたことがある。風の動 きさえない森は、いまにも木々の間から何かが襲いかかっ てくるような不気味さで、三人は見えない影から逃げるよ うにして、凹凸の山道を走り抜けた。両側にレンゲ畑が広 がる道を、時折り、馬車や自転車が通り過ぎていく。 三人は馬の手綱を引く大人の目を盗んで、馬車の荷台に 乗った。馬を操る大人も彼らに気づいていて、知らぬ顔を した。小さな橋にさしかかった。春の日に映えた水面がビ ー玉を散りばめたように輝いている。 3年生になって3ヵ月経ったころだった。文男は仲良し の進一や健二を急に避けるようになり、一人で下校するよ うになった。それにはわけがあった。校内の便所に行くの が恐い。便器にまたがると、天井や戸の隙間からだれかが 覗いているような恐怖感に襲われた。想像するだけで、い ままでなんともなかった下腹部が痛みだした。 「頭が痛いので、保険室へ行きたいんですけど…」先生に 断って授業を抜け出し、校庭の隅の林の中で用を足した。 水のような下痢であった。そうしたことも一、二度なら まだしも、何度も重なるうち、先生もクラスの生徒も彼の 頭痛を怪しむようになった。 どうか、下腹が痛みませんように……。しかし、祈りに も似た想いとは裏腹に、腹痛に襲われる回数は日ごとに増 していった。クラスの中で爆笑がおこると、それが自分の ことを笑っているような気がし、全身が硬くなった。 恥かしさから、誰にも相談できずにいた。仮に、だれか に相談し、妄想であるなどと説得されても、頑なに信じ込 んでしまっている幼い文男に、理解できるはずもなかった。 夏休みも近いある日のこと。帰宅途中、急に腹痛をおこ し、用を足すため適当な場所を探した。前日はなんとか民 家奧の林の中で用を足したが、この日はあいにく、辺りは 民家も多く、人通りもあって、そのまま歩き続けた。手に も額にも脂汗がにじみ、歩くのもやっとの状態で、必死に 耐えた。しかし、我慢にも限界があった。 下痢は突然、堰を切ったように吹き出し、そのほとんど はズボンを伝って道端に流れ落ちた。しかし、なにごとも なかったかように、そのまま歩き続けた。 自宅に着くころには、下着に付着した汚物も、なんとか 体裁がつく程度に乾いていた。帰宅するなり便所に駆け込 んだ。こわばった表情で落ち着かない文男に気づいた母が、 「どうしたの?」心配し、尋ねた。 なにも答えられずに、そのまま俯いてしまった。 その日以来、汚物で下着を汚すことが多くなった。母も たまりかねたのか、ある日、帰宅した文男の下着を脱がせ ると、「三年生にもなって!」便で汚れた下半身に、バケ ツの水を浴びせた。 帰宅途中のことは、クラスの生徒にもすぐに伝わった。 「西山、おまえ、ウンコしかぶったげなね」ふだん口もき いたことのない三郎が走り寄ってきた。分厚い唇のまわり には、意地そうな笑みが浮きあがっている。 一瞬、”しまった”と思った。他の者に知られても、三郎 だけには知られたくなかった。大柄で喧嘩も強い彼は、弱 い者いじめが三度の飯より好きで、同学年の生徒なら、知 らない者はなく、いつも子分を4、5人従えていた。 噂千里を走るというが、三郎にかかっては子分をして、 一日千里はおろか、三千も四千も走った。文男は三郎を無 視したように、足早ににその場から立ち去ろうとした。 「おまえ、恥ずかしいケン、逃げるとや?」三郎は責めよ るように言ってから、文男の前に立ちふさがった。 「おまえが道にクソばらまいて歩いとうとば見たモンがお るとぞ」三郎は膝を曲げ、おどけながら彼のまわりを二、 三周した。汚物にまみれて歩く文男の真似だ。恥ずかしさ のあまり、何もいわずに立っているのがやっとであった。 三郎のそばで文男の表情をのぞくように伺っていた栄作 も突然、猿のように中腰になって尻をうしろに突き出した。 便を漏らしたときの真似で、皆、大声で笑った。 文男は栄作を殴ろうと手を握りしめた。が、握りしめた 拳は動かせない。栄作を殴ったら、反対に彼らからなにを されるか分からない。笑われるまま、その場を離れた。 数日後、授業がひけ、校門を出る文男に、背後から声を かける者がいた。振り返らなくても、それが進一と健二で あることはすぐにわかった。教室から追ってきたのか、 「いっしょに帰ろう」息を弾ませながら言った。 毎日連れだって帰っていた彼らと下校するのは1週間ぶ り。みずから人を避けてきたが、それでも実際にひとりで 帰るとなると、これほど寂しいことはなく、それだけに、 声をかけてくれたときは内心、嬉しかった。 「どうしたん?。このごろ、元気ないよ」進一が心配げに 尋ねた。しかし、本当のこともいえず、文男はうつむき加 減の顔を進一に向け、無理やり笑みをつくった。 夏休みに入り、文男は本当のことを母に打ち明けた。 「そうだったの。かあさん悪かった。水をかけたりして、 ごめんなさいね」事情を知った母は、 しきりに謝った後、 「ウンチってだれでもするでしょ。反対になかったら大変。 ウンチくんとお友達になりなさい」そういって、微笑んだ。 夏休みも終ったある日、学校を出て3、40分。森を迂回 し、小さな橋を渡り、療養所の近くまで来た。広大な敷地 をもつ療養所は松林に覆われ、その奧に木造の建物がいく つか見えた。橋の手前の明るい風景とは異なり、人影もな く、静けさの底でトロトロ眠っているようであった。中に 入らないよう注意されていた。 「どうして、入っていけないのだろう?」文男にとって、 療養所は、まわりの社会と切り離された特殊な場所で、建 物や中に入る人たちに対する恐怖心とは裏腹に、好奇心だ けが日々、膨らんでいった。 下校時、文男と進一は網で囲まれた塀をくぐって、療養 所内に入った。松が群生する広大な地はコンクリートで舗 装された細い道以外は、いちめん芝生で覆われ、細長い平 屋建てが一定の距離を保ちながら立ち並んでいる。 人影はなく、不気味で、その不気味さが、さらに彼らの 好奇心をそそった。だが、透明ガラスの向こうは沈黙の中、 廊下が伸びているだけで、中の様子を窺い知ることはでき ない。二人はつま先を立て何度も覗きこんだ。淀んだ静寂 だけが彼らに応えるだけである。二人は病棟の合間をぬっ て、さらに奧へ進み、渡り廊下から中の様子を窺った。 「気持ち悪いね」廊下の向こうに何があるのだろう。 そのときだった。廊下の奥に白い影が動いた。 「きみたち、そこで何してるんだっ」 二人は渡り廊下から飛び出し、急いで木陰に隠れた。 「見つかった。近づいてくる!」一目散に逃げだした。 「中に入っちゃダメじゃないか」強い叱責を背に受けなが ら松林をぬって、塀の外に出た。 「なんだか、悪いことしたね」二人は顔を見合わせた。 空を見上げると、雲の一部が赤く染まり始めていた。二 人は帰路を急いだ。馬車や自転車に混じって、三輪車が砂 埃をあげながら、二人を追い越していった。 広大な療養所を囲むように伸びた道を北へ少し歩くと、 右手に病院関係者が住む平屋建ての官舎がみえてくる。 「何があったか知らんけど、最近、元気ないよ。元気だせ」 別れ際、進一はそういって、文男の肩を叩き、手を振り ながら官舎の中に消えていった。 進一と父親について話したことはないが、彼の住む官舎 は中でも比較的大きかった。中に何度か入ったことがある が、本棚や家具はかつて目にしたこともないものばかりで、 本棚には横文字で書かれた分厚い本が所狭しと並んでいた。 文男の背丈より高いボックス形の蓄音器やレコ-ドなども 目を引いた。さらに、彼の家から北へ数分歩くと、健二が 住む官舎があった。彼の家には入ったことがない。 その年の暮れ、父の浮気はなかなか止みそうになかった。 相手は生園良子という40過ぎの未亡人で、ほっそりした体 型のうりざね顔の人であった。が、切れ長の目、少々まえ に突き出た歯、お世辞にも美人とはいえなかった。よりに よって、どうしてこんな女性と付き合うのか、子供ながら に不思議でならなかった。 父と生園は文男と妹の亜子、それに生園の娘ふたりを連 れ、動物園へ行った。生園は文男には殊更、優しかった。 キャラメルやチョコレートなど、惜しげなく買い与え、 「ほらっ、赤ちゃん猿があくびした」などと言っては、突 きでた歯が気になるのか、右手で口を押さえながら笑った。 別れ際には文男たちを見送り、駅の売店で買った菓子を 与えた。菓子を手渡す生園のつくり笑いにも似た笑顔は、 「きょうのこと、おかあさんには内緒よ」そう語りかけて いるようであった。 なぜその日、父に付いて動物園へ行ったか、子供なりに 罪の意識はあったようだが、60数年以上も昔のことで覚え ていない。母がその日の事に気づいたかどうか分からない。 ただ、その日に父が撮った写真が何かの拍子に文男のア ルバムから見つかった。セピア色に変色した写真には生園 と二人の娘、それに文男たちが写っていて、なぜか、生園 の顔の部分だけが、なにかで削り取ってあった。 文男が中学生になって、なにかの拍子にその日のことが 話題になった際、母がひとことふたこと、その日のことを、 文男に尋ねた。笑いながら…。 父の浮気だけが表に出たようだが、父は争いを好まず、 寡黙な人であった。通信士と技術士1級の免許を持ってい たため、戦時中は商船に乗った。文男が成人になって叔父 から聞いた話だが、航行中、藻がスキュリューに巻きつき 航行不能になった際、鮫が多い海中に潜って藻を取り除い た。鮫は自分より大きなモノは襲わないらしく、数人の褌 を長く結んで体に巻き付け、潜ったらしい。 また、敵の魚雷が舷側に当たった際は、機密書類等を沈 めるため船長と最後まで船に残ったそうな。ほかにも室戸 台風時の人命救助など、叔父や叔母から聞いた話しは数多く いま私に家族があり社会の一員としておられるのは、ひとえに父と数学担任のおかげだといえる。高校生のとき、どうしてもピアノの練習をしたく、夜間、学校の音楽室に侵入。ピアノの音で当然、夜警に捕まった(お陰様でその後、音楽教師に可愛がられたが)。 このころ成績上位30人ほどが選ばれたクラスにいた私は遊びのようなカンニングで1週間の自宅謹慎。その夜、下宿していた悪友と酒を飲み、訪ねてきた教員に見つかり、退学処分の話が職員会議で検討された。
すぐに学校に謝りに行った父親。「私のクラスから退学者は出しません」数学の担任の返事だ。そういえば数学だけは他教科に比べ群を抜いていた。これは点数中心の傾いたやり方に反発していたころの話しで、高校を卒業してからも大学、就職と、父親にはなにかと心配や苦労をかけた。でも、争いを好まない寡黙な父はこんな迷える私にいつも言葉少なに寄り添ってくれた。ありがとう、おとうさん。 4章 龍ちゃん 町内に文男より一歳年上で金田龍次という少年がいた。 中肉中背で、顎骨のはった四角い顔には小さな目が申しわ け程度についていた。無口であったが、ナイフひとつで水 鉄砲や竹トンボ、凧や竹馬などなんでも作る手先の器用な 少年であった。彼にはふたりの妹がいたが、下の妹は生ま れてまもなく、親類の家に養女としてもらわれていった。 次女を養女に出したため、両親と妹の四人家族であった。 彼の父は戦時中、右手を弾丸で吹き飛ばされ、肘から下 がなく、先が釣り針状になった義手をつけていた。こまめ に働く人だったが、定まった職がなく、普段は日雇い仕事 や新聞配達、夏季には自転車の荷台に木箱を乗せ、アイス キャンデーを売りまわっていた。 「チリン、チリン」呼び鈴がなると、文男は昼寝から覚め、 母からもらった5円玉を握って外へ飛び出した。 「わたしもっ」妹の亜子も負けじと、兄のあとを追った。 いっぽう、龍治の母親は小柄な人だったが、男たち人夫 にまじって働いた。 春さきから夏にかけ龍次と文男は、しばしば小川へ魚と りに行った。療養所のそばを南から北へ流れる幅5,6メ ートルの川は、両側から柳や笹の小技が蒲鉾形に張りだし、 暑い日は、それが日よけにもなった。 ショウケを手にし、できるだけ水音をたてないように、 下流から上流へ移動する。10センチほどの鉛色の魚が物音 に驚いたように素早く川の中央に踊り出たかと思うと、す ばやく反対側のモノ蔭へ逃げこむ。 「あのへんから追ってくれ」中腰になった龍次が、10メー トルほど上流を指差した。文男は薮をかきわけ、一旦、土 手にあがった。魚に警戒されないためである。龍次が指差 した場所から、左右に行ったり来たりしながら、川下に魚 を追い込む。すばやく龍次が動いた。 「大きいぞー」龍次が叫んだ。文男は胸をときめかせなが ら龍次のいる場所に戻った。ショウケの中をのぞくと、中 には30センチほどの黒く大きな魚が、龍次の押えた左手の 中で、力いっぱい身をくねらせている。 「大きたフナやなあー」 「いや、フナじゃなか。口の横にヒゲがあるやろ」 「んなら、コイか?」文男が尋ねた。 「大きかなあ。死なんごと早う帰ろ」コイは窮屈そうに、 持ってきたバケツの中で体を丸めている。ふたりは、あぜ 道を小走りに龍次の家へ急いだ。 龍次の家に着くと、玄関先で、何度もバケツの中を覗き 込んでから、勝手の隅にある井戸の中へ投げ入れた。大き くはねる音がした。 勝手内は、小さな格子窓から差しこむ日の光だけでは、 足もとさえはっきりしない。龍次は背のびして裸電球をつ けた。斜めに差す電球の光が、湿気を含んだ土間に無数の 陰影をつくった。そのあと龍次は、踏み台を水屋のまえに 運び、棚の中から茶色の壷を取り出した。中には黒砂糖が 入っていて、中から卵大の黒砂糖をつまみ出すと、歯で半 分に割って、「食わんか」と言って、文男に差しだした。 「おれ、腹いっぱいやけん、いいよ」とっさにそう応えた ものの、黒砂糖などほとんど口にしたことがない。龍次は いやな顔をしたが、彼の好意を断るにはそれなりの理由が あった。つまみ食いする際、彼は辺りを気にしていた。 「泥棒猫みたいなことしてからに。今度したら承知せんか ら、わかったか」かつて文男の目のまえで、母親が彼を叱 りとばしたことがある。 「おれも、おやつが欲しいー」 「なに寝ごと言うとっとね。これは料理に使うとたい」 「みんなおやつ食っているのに、なんでぼくだけ……?」 「よそはよそ、うちはうち」悔しげな彼の顔だけが残った。 夏休みも終りに近づいたころ、龍次の父親に日雇いの仕 事が入った。代わりに龍次が夕刊の配達を始めた。配達区 域は彼の家から5、6キロ離れ、しかも広域にわたった。 龍次は自転車の荷台に新聞を山積みすると、ペダルをこ いだ。文男も子供用の自転車に乗って、あとを追った。 国道3号線を西へ向かって3キロほど走ると、古賀町の 商店街が見えてくる。道の両側に八百屋や雑貨店など色々 な物がそろったアーケード街である。 商店街に入ろうとしたときだった。横殴りの突風が襲っ た。風は新聞紙を宙に巻きあげ、紙ふぶきのように四方に 飛び散った。普段は冷静な龍次だったが、ただ呆然と立ち すくんだままだ。 「龍ちゃん」文男は龍次の背中を軽く撫でた。 「あ、ああ……」泣きだしそうな顔で、言葉もでない。 「とにかく拾おう」二人は近くに散らばった新聞から拾っ ていった。通りがかった人たちも手伝ってくれ、なんとか 回収した。それでも残りの10部ほどは溝に落ちたり、紛失してしまった。  昭和26年古賀町商店街(古賀市立歴史資料館から 昭和26年古賀町商店街(古賀市立歴史資料館から
「あー、もうだめや」龍次は絶望に似た声をあげた。しか し、嘆いていても仕方ない。ひとまずかき集めた80部を配 ることにした。手伝ってくれた人に頭を下げると、ふたた び自転車にまたがり、三号線を左に折れた。 南へ2キロほど走ると、古い民家が凸凹道の両側にポツ リポツリ建っている。人影もなく、緑に隠れて見えないが、 時折り、牛や豚の鳴き声が聞こえてくる。龍次は一軒一軒、 表札を確かめながら配ってまわった。日中の暑さが嘘のよ うである。赤トンボが目のまえを水平飛行した。 「もう夏休みも終わりやなあ」龍次が言った。そのとき文 男は忘れていた夏休みの宿題を思い出し、ため息をついた。 「おやじ、おこるやろうなあ」龍次もため息をついた。 逝く夏を惜しむかのようなつくつく法師の鳴き声もいま は止み、遠く西にかすむ立花山が黒い影を空に広げていた。 二人は龍次の家の近くの公民館の前で別れ、文男は薄暗 くなりつつある道を家へ急いだ。 勝手口から音を立てずに家に入ると、 「こんなに遅うまで何してたと?」背後から母の声がした。 「う、うん」返事だけして、すぐに母から視線を反らした。 母もそれ以上は聞かなかった。食卓につくと、急いで食 事を済ませ、宿題を抱え、机に向かった。 その年のクリスマス、夕方ごろから珍しく舞いだした雪 はひと晩で10センチほど積った。珍しい白銀の世界に、文 男は雪ダルマを作るため、さっそく龍次の家へ向かった。 龍治もちょうど、雪ダルマを作ろうと思っていたようで、 すぐに出てきた。ふたりで雪を丸め、転がしていると、 「ふみンとこ、サンタ、来た?」龍次が尋ねた。 「……。う、うん、来たよ」。「何もろうたと?」 「ネジで動く電車」。「おれにも見せてくれん?」 「いいよ」龍次は一瞬、悲しげに俯いて、 「おれんちには来んかった。いままで一度も来たことなか」 「ぼくん家と龍ちゃんとこ、あまり離れとらんとに、どう してやろなあ?」彼の家にサンタが来ないことが不思議で ならなかったし、龍次に対しすまない気持ちにもなった。 「もしかして煙突にススがたまっとるけん、サンタ、入れ なかったかも知れんな」そう言って龍次は寂しげに笑った。 9時を告げるサイレンがなった。そのとき、新聞を配り 終えた龍治の父親が家に戻ってきた。雪のため、いつもよ り配達に手間取ったのだろう。頭からかぶった雪を玄関先 ではらい落とすと、ふたりの方をチラっと見てから、うす 暗い家の中に入っていった。龍次は雪ダルマを作るのを止 め、父親を追うように家の中に入っていった。 父親は畳の部屋の真ん中であぐらをかき、火鉢の炭をか き混ぜながら、その炭で煙草に火をつけようとしていた。 「とうちゃーん」。「なんや?」 「ぼくん家だけ、どうしてサンタさん来ないと?」父親と 一定の距離を保ち、恐る恐る尋ねた。 「サンタクロース!なんば寝ごと言うとんのか」 キセルを火鉢の隅でたたくと、外へ出ていった。以来、 龍次とはクリスマスの話しをしたことがない。 龍次の父は、その後、数年して亡くなった。新聞配達の 途中、事故にあったそうだ。戦時中に失った右手、荷台に 山のように積んだ新聞の束。三号線を走っている姿は、幼 い文男の目にも、日頃から危なっかしいものに映っていた。 彼はいま、郊外レストランの店長を任されている。酒は たしなむ程度で、30歳で家を建てた。先日、宗像の彼に電 話した。あいにく不在で、代わりに母親が電話口にでた。 「おかげさまで、ひと月まえに孫が生まれまして……」 嬉しそうに話す母親の声は、心なし若やいで聞こえた。 息子に頼れる幸せが、受話器を通し伝わってくる。
5章 草野球 昭和31、2年といえば、福岡にホームグラウンドをおく 西鉄ライオンズがジャイアンツをくだし、二年連続日本一 の栄冠に輝いた年である。奇跡の逆転優勝をなしとげたラ イオンズは、当然地元に住む子供らの憧れの的であった。 子供らは学校の行き帰りに、だれだれがホームランを打 った、ファインプレーをしたなどと、毎日のように野球の 話しで盛り上がった。遊びも野球に落ち着いた。 夏休みに入った。朝食のあと文男はグローブを持って家 を出た。広場には、すでに十数人集まっていた。軟球だが、 ピッチャーは球を下からすくうように投げるため、ソフト ボールと草野球の中間といったところだろう。 「ショートにだれもおらんけん、おまえ守ってくれ」ひと つ年上の富田がいった。ショートへ向かって走った。青く 澄み渡った空の下、子供らの掛け声が辺り一面に響く。 敏明がちょうどバッターボックスに立った。四年生のわ りに大柄で、運動神経も抜群。よく打ち、よく守った。 敏明は初球をすかさず打った。バットの真芯に当った打 球は守備についたばかりの文男の正面で鋭角にバウンドし た。あわてて2、3歩後進した。が、ボールは股間を抜け、 はるか後方の道路わきの溝に落ちこんで止まった。 「ふみっ、腰が高いぞ」三塁を守っている富田が叫んだ。 5対5の同点だっただけに、悔しそうである。 7回の裏、6対5でリードされた富田チームの攻撃。ワ ンアウトから富田がボックスに立った。一球目ボール、二 球見逃し。そして、三球目高めのストライクを、三塁側へ 引っぱった。痛烈な当たりである。しかし、サードを守っ ていた敏明が飛びつき、シングルキャッチした。 打球も強烈なら、敏明のプレイも見事なものであった。 「よか当たりやったがなあ。さすが、としあき」 ツーアウトから文男がバッターボックスに立った。 「さっきの名誉挽回や」そう自分に言い聞かせながら、肩 の力をぬいた。いつもよりバットを短く持って構えた。 一球目空振り、二球ボール。三球目を力いっぱい振った。 手応えは十分。間違いなくホームランである。しかし、ボ ールの落ちる場所が悪すぎた。トタン屋根が音をたてた。 「あっ、しもうた!」文男と同時に、だれかが、 「じいさんが出てくるぞ。逃げろっー」大声で叫んだ。 「おまえら、なんかい言うたら分かるんかーっ」飛び出し てきたのは梅田のじいさんである。全員、バットやグロー ブを手に取ると、一目散に松林の中へ逃げこんだ。息を切 らせながら走ってきたじいさんは、松林の手前で、悔しそ うにこちらを睨んでいる。 「こん(の)まえは窓ガラスを割って、いい加減にせんかっ」 おじいさんは梅田虎吉という。”虎になる”というが、こ の日も朝から酒を飲んでいたのか、千鳥足であった。おま けに手には木刀を持っている。肉をけずり落としたような 痩せた顔に隈のできた目の縁、濁った瞳は、別世界に住む 人という印象で、近所付き合いも、ほとんどなかった。 松林を抜け、公民館のそばまできた。この一帯は、小さ な松が群生し、夏は夕涼みに絶好の場所である。 「ひやーっ、恐かったたあ」砂の上に皆、腰を落とした。 「これで何回めか。もう、あそこで野球できんばい」富田 が額から吹きでる汗をランニングシャツの裾でぬぐった。 「あのへんちゅくりんのじいさん、仕事もせんと酒ばっか し飲んどおけん、バチの代わりにボールが当ったんや。あ ん音はホームラン賞の音たい」敏明の言葉に皆、腹を抱え て笑った。林を抜ける風が、汗ばんだ肌をなでていく。 秋の気配が濃くなっていく9月になって、梅田のじいさ んが突然亡くなった。近所の入が町内会費を集めに行き、 たまたま、おじいさんの死に気づいたという。 公民館そばの松林を抜ける風も、心持ち肌寒い。 「梅田ンじいさん、死んだげな」敏明が言った。 「なんで死んだんか?」富田が敏明の顔を覗き込んだ。 「かあちゃんが、ロウ、老ソウとか言うとったばい」 「そりゃ老衰の間違いやろう」富田が笑った。 「あ、ああ、そうそう」敏明が頭をかいている。 「老衰ってなーに?」そばから勝治が尋ねた。 「年を取り、体が弱って死ぬことや」 「ふーん」富田の返事に勝治がうなずくと、 「これで、思いきり、野球できるぞう」秋の弱々しい日差 しをはね返すような敏明の弾んだ声に、皆、 「そう、そう。良かった、良かった」嬉しそうに応えた。 翌日、広場はふたたび子供らの声で満ちた。敏明がバッ ターボックスに立った。力いっぱいのスイング。彼が打っ た球は大きく道を越え、じいさんの家のトタン屋根にあた り、激しく音をたてた。 「ヒーッ、じいさんが来るぞーっ」勝治の大声に、皆、じ いさんの家を見つめた。だれかが、 「勝ちゃーん」すでに松林の中に逃げる勝治に言った。 「じいちゃん、もういないよ」皆、笑った。しかし、笑い は風船がしぼむように、すぐに萎えてしまった。 「なんか寂しかなあ」じいさんの家の方を見やりながら、 富田が言った。顔を赤らめ、木刀を手にした姿は、いまは ない。それから2、3か月のち、その家は取り壊された。 これは後日、文男が母から聞いた話だが、梅田虎吉さん は終戦の前の年、ビルマ戦線で一人息子を亡くしたという。 ジャングルで食料も途絶えた中、「戦病死」だったそうだ。 それに、奥さんも空襲で、燃え盛る炎の中に失ったという。 文男にとっては、大酒呑みで、怒った顔しか記憶にない が、母はおじいさんについて、 「よく飲んでらっしゃったけど、息子さんたちのお墓参り は、毎日、欠かさず行ってらっしゃったね」 母の話しを聞きながら、文男は神経質で恐そうなおじい さんの顔に、いつしか弱々しい一縷の涙を配していた。
6章 勝ちゃん 昭和33年、まわりの暮らしも少しずつ楽にはなっていた が、それでもテレビや車などほとんどない時代であった。 町内の子供たちのあいだで自転車が流行った。どの家も、 すぐに自転車を買う余裕などなく、子供たちは、黒く荷台 が大きな大人用を借り、乗った。上級生にはサドルに跨れ る子供もいたが、多くは横乗りといって、ペダルの上の三 角形のフレームのあいだに右足を入れ、漕いだ。 文男の家は自転車がなく、母親は苦しい家計の中から子 供用自転車を買い与えた。その時の嬉しさはかつて経験し たこともないほどで、空が白む頃から自転車に触れた。 ある日の夕刻、サドルにまたがる練習に汗だくになって いると、同級生の敏明が、軽々と自転車にまたがり、 「フミっ、だいぶ乗れるようになったな。無理すんな」 口笛を吹きながら通り過ぎていった。 (くそーっ、敏明の馬鹿たれが) 成績が良く運動も抜群の敏明……。その彼とは対照的で、 山下勝治という勉強が苦手な少年がいた。小柄で、お日さ まに似た丸顔、ドングリのような瞳がいっそう愛嬌あるも のにした。彼のことを皆、「勝ちゃん」と呼んだ。 「勝ちゃんとこのおっちゃん下手くそやけん、散髪に行か んごと、かあちゃん言うとったばい」敏明が冷やかしたよ うに言うと、そばにいた子も、 「そうや、そうや。勝ちゃんとこに行くと、虎刈りにされ るもんな」まわりの子もつられて、大声で笑った。 「とうちゃんは下手じゃなか。慎太郎刈りやったら、だれ にも負けん」真面目顔になった。気弱な勝治がそうして挑 んでくるような態度が皆を、さらに愉快にした。 「慎太郎刈りやのうて、虎刈りの間違いやろ」敏明の言葉 に、「そうや、そうや」まわりの皆が声をあげた。 「んにゃ。とうちゃんな、腕がいいから、毎日お客さんも 多かと。皆が言うごと、下手じゃなか」 「皆、行こ。勝治といたらアホになる」敏明が言った。 (勝っちゃん、やっぱりアホかなあ)文男も内心、思った。 ある日、いつもの空き地で野球をしていると、自分の背 丈ほどもある自転車を押し、勝治がやってきた。 (あの勝ちゃんが……)皆が驚いたのも無理はない。ボー ルがバットを掠めたことすらない勝ちゃんだったからだ。 「勝ちゃん、おまえ自転車に乗れるんか。知らんかったあ」 「う、うん。乗れるよ」 「ほ、ほんとか。すごいなー。じゃ、見せてくれ。みんな 見たいなあ」敏明はそう言って、皆の方を振り返った。 「でも急な坂だし、危ないぞ」富田が心配して言った。 「富ちゃん、オレ、ほんとに乗れる。だいじょうぶ、だい じょうぶ」空に目線を移し、胸をはった。草野球をやって いる広場の横に幅4、5メートルほどの道が国道三号線か ら北へ2,3キロのび、その中程に二百メートル程の緩や かな坂道がある。その坂を駆け降りるというのだ。眼下に は一面、ナスやキュウリ、トマト畑が広がっている。 勝治は左足をペダルに掛けると、右足で小刻みに土を蹴 り、坂道にかかった。坂道で勢いがついた自転車は、さら に風をきって一直線に伸びていく。 「す、すごいなあ」だれかが言った。 「ぶったまげたー」敏明も次第に小さくなっていく勝治を 驚いた様子で見つめている。坂を下りきった彼はやがて、 自転車を押し、息を切らせながら戻ってきた。 「勝ちゃん、すごかなあ!」富田も自分のことのように喜 び、勝治も得意気にふたたび胸をはった。 「よかったら、今度はオレをうしろに乗せてくれんね」 敏明がいった。富太が止めようとした。 「いいよ。オレ、妹を荷台に乗せたことがあるけん」 そのとき敏明は、すでに坂道の中程へ向かって走り出し ていた。また、勝治も右足で地を蹴った。坂道を10メート ルほど下り、さらに自転車はスピードを増し、待ち受けて いた敏明が荷台に手をかけた。その瞬間、荷台が敏明の体 を弾くように左右に揺れ、左手の土手下に自転車もろとも 消えてしまった。すぐに道へ這い上がってきた敏明が両手 で股間を押さえ、痛そうに道の真ん中で飛び跳ねている。 「だから、言うたろうが」富太は勝治が消えた畑へ向かっ て走り出した。皆も富太のあとを追った。ところが、勝治 の姿が見あたらない。そのとき、だれかが、 「なんか、臭せえなー」そう言って、鼻をつまんだ。同時 にそばにいたひとりが、「大変だー」叫んだ。 勝治が肥え溜めの中で声も出せずに両手をばたつかせて いる。たて横4、5メートルもある肥え溜めは表面が茶褐 色に凝固し、彼がもがいている箇所だけが穴をあけたよう に丸くなっている。勝治がばたつく度に、汚水がまわりの 黒ずんだ凝固物の上に飛び散る。 「その辺に、長い棒はないか?」振り返った富田に文男は トマト畑の支柱を指さした。 「あれで良か。早う、取ってこい」 富田は文男から竹棒を受け取ると、 「勝治、しっかりしろ!。早よう、これにつかまれ」 勝治の首筋あたりに棒を引っ掛けようとする。しかし、 し尿を含んだ服が重過ぎるため、うまくいかない。 そのうち勝治の両手の動きが鈍くなり、やがて力尽きた ように浮き沈みはじめた。富太は棒で勝治の坊主頭を強く 叩いた。瞬間、勝治の両手もふたたび動き始め、富田が差 し出した棒を右手で握った。 「そうそう、離すな!。……。皆、勝治に声をかけろ」 「かつじ、勝治っ」大合唱が始まった。ゆっくり手もとに 手繰りよせる。富田が勝治の右手をつかんだ。 「敏明、勝治の左手を引っ張れ」富太がいった。だが、敏 明は汚れた手に触れたくないのか、尻込みし、動かない。 「はよ、せんかっ」富太が怒鳴った。 「いいか。いち、にいのー、さんで引っ張るぞ」富太は勝 治の右手、敏明は左手を掴んで手元に引き寄せる。異臭を 放つ汚物が二人の洋服に飛び散って、ようやく、勝治は肥 え溜めから助け出された。 しかし、汚物でミイラのようになった勝治は、畑の上に 横になったまま動かない。富太は脱いだ上着で勝治の顔や 頭を拭いたのち、うつ伏せにし、馬乗りになって背中を押 しはじめた。富田が押すたびに、勝治は飲み込んだ汚水を 苦しそうに吐き出していく。 そのとき、土手の上を通りかかった男が騒ぎに気づき、 走り寄ってきた。がっしりした体に角刈りの男は山本政春 といい、青年団の団長をしていた。ふだんから子供たちに 野球を教えたり、皆を海水浴に連れていく面倒見の良いお じさんであった。日ごろから子供たちは、男のことを、 「政おいちゃん」と呼んでいた。政おいちゃんは、まだ汚 物の残った顔をみて、頓狂な声をあげた。 「こりゃ、勝治やないけ。また、どうしてこうなった?」 子供らは答えることもできず下を向いたままである。 「とにかく、こんままじゃ、車には乗せられん。 敏明っ、これから駅前のため池に運ぶんで、消防団の重 松さんば呼んでこい。事情を話し、くるまで来るようにな」 「う、うん」。「うん、じゃなか。はいと言え」 「いいか。駅まえのため池ぞ。分かったな」 「それから、健っ。おまえは勝治のおやじさんに知らせろ」 敏明に続き、健一も土手の向こうに消え、皆がふたたび 勝治に視線を移した。そのとき、 「政さーん、どうしたとなあ?」道の方を見やると、リヤ カーを引いた半白髪の老人が立っていた。 「あっ、こりゃ、トメさん。散髪屋の勝治が肥溜めン中に 落っこちたですたい」 「まっ、また、どげんしよって?」 「話はあとで……。勝治ば、駅まえのため池に運びたかと です。よかったら、リヤカーを貨してくれんでしょうか」 「よかよか、どうぞ使いなっせ」 そのうち、ようやく勝治は意識を取り戻したようで、 「かあちゃーん」大声で泣きだした。 「よかよか、だいじょうぶ」勝治の泣き声に政おいちゃん も、ほとほと弱りきった様子だ。おいちゃんは庭職人で、 ふだんから紺の印半天に地下足袋すがた、腰にタオルを下 げていた。タオルで勝治の体をぬぐうと、 「すぐ良くなるけんな」勝治を抱きかかえて土手を這いあ がり、リヤカーに寝かせた。リヤカーを引っ張り、おいち ゃんが走る。皆もあとを追う。 坂道を北へ走ると、醤油工場の門前に出る。松林に隠れ るように建った古い工場。その手前を右折すると西鉄宮地 岳線の花見駅がみえる。左手は白砂の上に松林が広がり、 海からの風に、その幹を仁王像のようにくねらせている。 目的のため池は駅前の道を挟んで右手にあった。周囲2、 3キロ、深さ5メートルほどのため池は、わずかに水を残 していた。リヤカーから勝治をおろし、池の土手を下った。 澄み渡った青空に入道雲が白く立ち上がっている。 勝治を池の畔に寝かせ、体を洗っていると、消防団の人 が数人、消防車でやってきた。中に勝治の両親もいた。 「政さん、えらいお世話になって…」 「いや、子供たちがみんなで、頑張ってですね…」政おい ちゃんは、照れたように頭を掻いた。そのとき、 「かあちゃーん」勝治は泣きながら母親の胸元へよろけた。 母親は用意してきたタオルを広げ、息子を抱き入れた。そ のとき、敏明の両親が息を切らせながら駆け下りてきた。 「なんちゅうことをしたんや」敏明の父は息子を一喝し、 勝治の両親に強ばった顔を向け、深く頭を下げた。 「話しは消防団の重松さんから聞きました。ほんに申しわ けないことをして、なんてお詫びしていいもんやら……」 「いやあ、敏ちゃんは元気が良うてよか。そのくらいなく ちゃあね」勝治の父は笑いながら、息子に目線を移した。 「ほんに、申し訳ありません」敏明の母親も勝治の両親に、 そのあと、皆に向かって深く頭を下げた。 「敏ちゃん、だいじょうぶだよ」大きな瞳をくるくるさせ、 口を開いた勝治の明るい声が、まわりの張り詰めた空気を やわらげ、敏明の表情にも笑みが戻った。 「いいえ、こちらこそ仲良くしてもらいませんと」敏明の 母も緊張した顔に笑みを浮かべた。 「この子は、根に持つような子じゃありません。すぐにケ ロっと忘れてしまうたちなんで……。ただ、勉強も学校に 忘れてこんと、ほんに良かとばってですねえ」小太りで、 人の良さそうな勝治の母親はそう言って、笑った。 「じゃ、そろそろ行きますか」消防団のひとりが言った。 「お世話おかけします」勝治の母が、消防団の青年に頭を 下げた。勝治と彼の両親を乗せた車は砂埃をあげ、醤油工 場の向こうへ走り去った。 父の転勤で、その後、大分、鹿児島と移り住んだ文男は、 40年ぶりに、思い出の地を訪ねた。宮地岳線、車窓の左手 に広がる松林。車内ではしゃぐ子供たちは、そのまま40年 前の自分であった。座席に腰をおろし、まぶたを閉じると、 遠く過ぎ去った子供のころの思い出。富太や勝治、敏明の 顔が回り燈篭のように次々に浮かんでは消えていった。 電車が目的の花見駅に止まった。松は昔のままにその身 をくねらせ、白砂の上に力強く立っている。蝉しぐれがひ とつになって聞こえてくる。電車から吐き出される人混み の中に顔見知りの人を一抹の期待をもって探した。が、見 知らぬ顔が通り過ぎていく。駅の正面。かつて勝治を洗っ たため池はすでになく、駐輪場の向こうは夏の強い日差し を浴びた屋板瓦が鏡を並べたように輝いていた。 足は、勝治の家の方へ向いた。途中、何人かとすれ違っ たが、なぜかよそよそしく感じ、数10年の歳月は自分をよ そ者に変えてしまったようにも思えた。思い出のつまった 風船が急速に萎んでいくようであった。 道を間違えたり、住宅街の袋小路にぶつかったり、通り すがりの人に尋ねながら、やっとのおもいで勝治の家の前 まで来た。思わず足をとめた。細々とやっていた床屋は、 拡張され、窓に映った明かりは夏の日差しをはね返すよう に明るい。文男は勝治の店に入るのを止め、隣の駄菓子屋 に入ることにした。幼いころ世話になった店で、なにもか もが変ったなかで、不思議と駄菓子屋の建物だけが昔のま まであった。 駄菓子屋に入ると、店の奥から小柄なおばあさんが、両 手と膝で体を引きずるようにして店先に出てきた。一瞬、 店の主が変わったのかと思った。が、よく見ると、子供ら に飴やスルメを売ってくれたあのおばさんである。染みや 皺が目立つ。曲がった腰。ただ、わずかに突き出た前歯と 細っそりした顔の輸郭が、そのまま昔の面影を残していた。 文男は名を名乗ろうとして、思いとどまった。なぜ素直 になれないのか、気恥ずかしさからか、申しわけない気も したが、通りすがりを装い、 「隣の床屋さん、ずいぶん大きくなりましたねえ」少し耳 が遠くなっているようで、ふたたび、声を大にして言った。 「あ、ああ、隣の山下さん?」 「え、ええ」やはり、あの勝ちゃんの店だ。 「山下さんが店を大きゅうしたのは、もう、ずいぶん昔の ことですよ。お知り合いですか?」 「え、ええ。ずいぶん昔になりますが、よく散髪してもら っていたもので、懐かしくなりまして……」 「それは、それは」 「私と同じぐらいの年で、勝治さんって人、いましたよね」 「ああ、勝治さんなら、いま店にいるんじゃないでしょか」 「勝治さん、頑張ってらっしゃるんですね」 「真面目で、それになかなかやり手なお人でね」おばさん の話しでは、勝治は近くにもう二つ店を出しているそうだ。 「他の店は、妹さん夫婦に任せていらっしゃるようで」 「それにしても、たいしたものですね。 立ち入った話ですが、じゃあ、おとうさまは?」 「なにもかも勝治さんに任せ、隠居の身ですよ。毎日のゲ ートボールが楽しみみたいですよ」そのとき、 「おばちゃーん、アイス、ちょうだい」7、8歳の男の子 と2、3歳の女の子が元気に入ってきた。小麦色に日焼け した賢そうな顔。ふたりとも大きな瞳が愛らしい。 「はい。いつものアイス、2本ね」 男の子はアイスを受け取ると、女の子に手渡し、二人は ふたたび炎天下へ消えていった。 「勝治さんの子供さんですよ」 幼いころの勝ちゃんとは似ても似つかない顔立ち。ただ、 どんぐりのような人懐っこい瞳は父親そのままであった。 文男はいつしか、目鼻立ちのすっきりした、優しいまなざ |