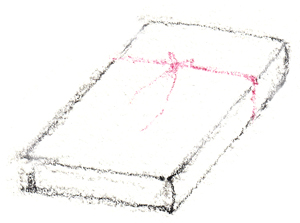3
仕舞いこもうと思ったものがあった ところがそれを納めるちょうどいい箱がない そうなると、あそこに行くしかない しんしんと雪が降る中、分厚いパーカーを羽織り(内側は朱色のボアだ) ブーツをはいて外へでた 歩いて十五分のところに、箱屋があるのだ 文字通り箱を扱っている店である これこれを入れる、こんな箱、とカウンターに座る主に言うと 刷り硝子のはめ込まれた引き戸の向こうから ぴったりの箱を持ってくる さらに、こんな風に包装したい、というと また引き戸の向こうに引っ込んで、 言葉通りの包装紙(グラシン紙や、蠟引きの紙、星空模様の紙など) とリボン(光沢のあるもの・ないもの)を持ってでてくる 先日、細い月の夜に店を訪れた時は 幼子の為に経帷子を縫った針を 納める箱が欲しいと言う老婆が先客だった 主はいつものように無言で引き戸の向こうへ引っ込み やがて小さな細長い箱を手に戻ってきた それは蝶番箱で、開けると中には柔らかな雪の結晶が 何層にも重なっていた 主は老婆から静かにその一本の針を受け取ると 丁寧な手つきで箱の中に横たえた 細く白い絹のリボンを結び、老婆に返す 老婆は涙に濡れた顔で頷き、大切に懐へ仕舞うと 店を出て行った さて、日没前の夕暮れとはいえ、 雲は厚く、すでに辺りは仄暗い 段々坂をのぼり、すれ違う人のない路地をゆく やがて、一軒の小さな店の前に辿り着いた 窓から明かりが漏れ、わたしは軒先で服の雪を払い がらりと扉を開ける 主はいつもの通り、カウンターの中におり、 本から顔をあげ、「いらっしゃい」と 大きくも小さくもない声をわたしにかけた 店は狭く、カウンターと壁に備え付けの棚があるくらい そこに色も形も多様な箱が詰め込まれている が、大抵この店に来る客は自分で箱を探すことはせずに、 主に依頼をするのだ 「これを」 カウンターに歩み寄ったわたしは、首の後ろに手を回し 付けているネックレスをはずそうとした が、凍える空気の中を歩いてきたせいで、手はかじかみ うまく留め具をはずせない 主はメガネを軽く押し上げて、カウンターの向こうから 取りましょう、と言った わたしはパーカーを脱いで後ろを向く 冴えない風貌の青年が器用なことは知っている あの繊細に箱を包む手を見ていればわかることだ 取れました、という言葉と同時にネックレスは手の中に落ちてきた 主に向き合ってそれを差し出す これを入れたいんです 主は黙って受け取るとわたしを見た やっと「わたし」に戻ることにしたのです ポケットから小さな袋を取り出すと、中身を掌に開ける はずしたネックレスと全く同じ形の、 わたしの名前が彫られた金色のプレート 姉の年に追いつきました 呟きに主は何も答えない 彼の手にある姉の名が記されたプレートには、 まだおそらくわたしの体温が残っているだろう しばしの沈黙の後、いつものように引き戸の奥に引っ込み そして小さな箱を持って来た それは一見白い本のように見える形の箱で、 蓋を開けると、白砂が敷き詰められていた 主はネックレスを砂の上にそっと置く どこからか取り出した純白の真綿をかぶせ、蓋を閉じる 桜色の糸をかけて封をした いかがでしょう、 …ありがとうございます 受け取って窓の外をみると、漆黒の闇 雪は止んだようだ ストーブの音だけがやけに大きく聞こえる もう、そんな年になったんですか、 ええ、と外を見たまま問いに答えるわたし 早いですね ええ、本当に 四年、経ちますか、 経ちましたね 一呼吸置いて …もう、そろそろ答えていただけませんか わたしはまだ窓の外を見ていた …そう、ですね あの日に聞くはずだった答えを、彼は淡々ともう一度乞う まるで四年の空白などなかったかのように あの日と同じ口調で 姉の想い人が誰かを知っていたわたしは、 姉が病で亡くなってから、それをずっと留め置いてきた けれど、 けれども わたしはやっと振り向く 変わりませんか、四年経っても …変わりません …そう、ですか わたしは息を吸う 次の言葉を紡ぐ為に 掌の小箱は棺のようだと思った 姉はきっと知っていた わたしの心も、彼の心も 帷っちゃんの好きになさいね 最後の言葉は多分そういうこと それでも時間はかかって、夜が過ぎ昼が過ぎ 夏が去って秋が去って 雪の夜を幾晩も経て わたしはここに立つ 止んだと思った雪がまた降り出している 窓硝子は曇り、何もかもを白く化粧(けわい)させてゆく 音のない夜のはじまりは しめやかな物語のはじまり 店先の白熱灯が、暗闇の路地をひっそりと照らしている